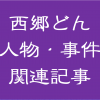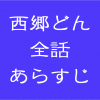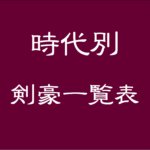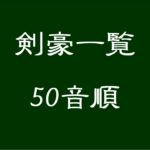大河ドラマ西郷どん(せごどん)
徳川慶喜(慶喜②)
大河ドラマ西郷どんで、重要な役割を担うのが徳川幕府最後の将軍・徳川慶喜。
最終的には倒幕を目指す薩摩藩にとって徳川慶喜は最大の敵になりますが、実はこの徳川慶喜は将軍になる前の「一橋慶喜」時代に西郷吉之助(隆盛)と出会って様々な経験を共にしています。
将軍になってから徳川慶喜と西郷吉之助(隆盛)の個人的な関係はどうなっていくのかわかりませんが、そこがまた楽しみなところにもなりそうです。
今回は、将軍に就任し「一橋」から「徳川」となった徳川慶喜について、将軍就任後~最期まで簡単に紹介します。
将軍就任前の慶喜はこちら
徳川慶喜役 松田翔太

徳川慶喜(一橋慶喜)②
家茂の死去に伴い、将軍となった慶喜は会津藩・桑名藩の支持のもと朝廷との連携を重視し、幕臣の多くを上洛させて政権の畿内移転を推進した。
また、慶喜は公家から側室を迎えて、将軍と関白・摂政を兼任する構想を立てる。
さらに慶喜はフランスから援助を受けて、横須賀製鉄所や造船所をなど設立し、陸軍総裁・海軍総裁・外国事務総裁なども設置するなど様々な改革を行っていく。
問題になっていた兵庫の開港については、慶喜は巧みな話術で朝廷から勅許を得ることに成功。
勅許を得ないまま開港すると予想していた薩摩・越前・土佐・宇和島の四侯会議は、慶喜を糾弾することができず解散となった。

出典:http://www.kurofune-shachu.com/
四侯会議解散後の慶応3年(1867年)、薩摩・長州両藩が武力倒幕を掲げると察知した慶喜は、先手を打って明治天皇に政権を返上する(大政奉還)。
慶喜は朝廷には行政能力が無いため、形が変わるだけで徳川家が主導する政治体制が存続すると考えており、大政奉還は内乱の発生も防ぐ「平和革命」であった。
この大政奉還により政治体制は諸侯会議に替わるはずだったが、旧幕府勢力が残ってしまうことは薩長にとっては非常に不都合な話だった。
このため、薩長は政変を起こして朝廷を制圧、慶喜を排除して新政府樹立を宣言する(王政復古)。
さらに新政府会議において、慶喜の「辞官納地(内大臣辞職、幕府領の奉納)」を決定した。
これに対し慶喜は、衝突を避けるため会津・桑名藩兵とともに大坂城に退去し、諸外国の公使らを集めて自らの正当性を主張。
「平和革命」を目指した慶喜に同情する藩が出始め、越前藩や土佐藩らが運動して慶喜の新政府への参画を確定させる。
追い詰められた薩摩藩は状況を打破すべく、将軍不在の江戸で過激派浪士を集め、挑発行動を行って武力衝突を誘った。
慶応4年(1868年)、江戸での薩摩藩の挑発に耐えていた大坂城の旧幕府主戦派はついに怒りが爆発、「討薩の表」を掲げて会津・桑名藩兵とともに京都に向け進軍した。
しかし、鳥羽・伏見の戦いにおいて旧幕府軍は敗退。
慶喜は兵力を十分に保持しているにも関わらず、旧幕府軍の兵には「決して退いてはならぬ」と厳命する一方で、自分は側近や妾など主要メンバーをと引き連れて開陽丸で江戸に退却した。
この時、開陽丸艦長の榎本武揚には江戸への退却を伝えず、武揚は戦地に置き去りにされている。
慶喜がとったこの行動には幾つかの説があるが真相は謎のまま。

出典:http://www.tokyoartbeat.com/
その後、慶喜を朝敵とする追討令が正式に下って、東征大総督・有栖川宮熾仁親王に率いられた新政府軍が江戸に向かって進軍を開始。
江戸に戻った慶喜は、徹底抗戦を主張する家臣たちを抑えて朝廷への恭順を主張し、事態収拾を勝海舟に任せて上野の寛永寺で謹慎した。
この時、徳川宗家の家督は養子の田安亀之助(後の徳川家達)に譲っている。
そして江戸城は、勝と西郷隆盛との会合によって新政府軍に明け渡された。
江戸城を明け渡したものの旧幕臣の中には抗戦派が残っており、暴発を恐れた慶喜は江戸から水戸に引き揚げて謹慎する。
さらに徳川家が駿府に移封されると、慶喜も駿河に移って謹慎を継続した。

明治2年(1869年)、戊辰戦争の終結を受けて謹慎を解除された慶喜は、そのまま静岡(駿府から改称)で暮らした。
慶喜は政治的野心を完全に捨てており、隠居手当を元に写真・狩猟・投網・囲碁・謡曲など趣味に没頭。
静岡の民衆から「ケイキ様」と呼ばれて親しまれた。
一方で慶喜は旧幕臣の訪問を受けても会おうとせず、共に静岡に移り住んだ旧家臣達が貧困に苦しんでいても無関心で「情を知らず」と罵られていた。

明治30年(1897年)に東京の巣鴨に移り住んだ慶喜は、翌年に旧江戸城に参内して明治天皇に拝謁。
明治34年(1901年)に小石川区小日向第六天町の屋敷に転居し、翌年に徳川宗家とは別に徳川慶喜家を興して貴族院議員に就き、35年振りに政治に携わった。
明治43年(1910年)、家督を七男・慶久譲って隠居。
慶喜は再び趣味に没頭する生活を送って、大正2年(1913年)に死去した。享年77歳。
慶喜は朝敵とされた自分を赦免してくれた明治天皇に深く感謝し、自分の葬儀を仏式ではなく神式で行なうよう遺言していた。
このため、慶喜の墓は徳川家菩提寺である増上寺でも寛永寺でもなく、谷中霊園に皇族と同じような円墳が建てられた。
慶喜の大坂での「敵前逃亡」は敵味方の両方から非難されたが、のちの慶喜の恭順により、京都や江戸は焦土とならず、外国の介入もなかったことから、国を守った維新最大の功績者の一人ともいわれる。
将軍就任前の慶喜はこちら